事 業 の 実 施 状 況 に つ い て
① 実施テーマ
基礎杭施工に伴う「杭単品個体の自動計測検査装置」の商品開発による販売及びリース・レンタル事業を目的とした事業体の設立
② 事業の具体的な取組内容
技術開発推進分科会としての事業の具体的な取組内容
今年度の「自動計測検査装置」に関する具体的な取組内容は、次の流れで進めた。
(1)ターゲットとする施工法の選定
(2)検査項目の選定
(3)検査項目の具体的な計測項目・センサーやパソコンのデイスプレイへの出力画面
の検討
以下には、上記の3項目の、それぞれの詳細について記載する。
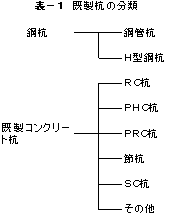 (1)ターゲットとする施工法の選定
(1)ターゲットとする施工法の選定
杭は製造場所によって、工場で製造される杭と原位置で製 造する杭に分類される。工場で製造される杭には、表-1に 示すように既製コンクリート杭と鋼杭があり、総称して既製 杭といっている。原位置で製造する杭は、地盤を掘削して掘 削孔中に鉄筋コンクリートを造成する場所打ちコンクリート 杭がある。表-2は、既製杭と場所打ちコンクリート杭を施 工法で分類したものである。
表-1、および表-2に示しているように、杭には、製造
場所や施工法によって、何種類にも分類できる。そこで、本
事業では、その中から近年市街地において、鋼管杭で主流を
なしている中掘り先端拡大根固め工法にターゲットを絞って
「自動計測検査装置」の商品開発に取り組むことにした。
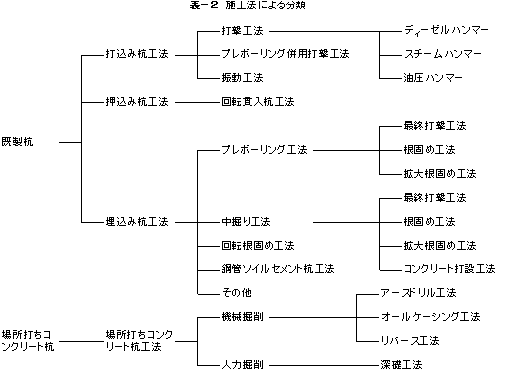 |
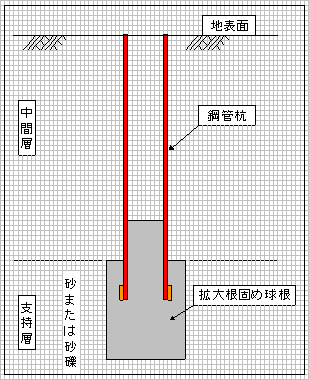
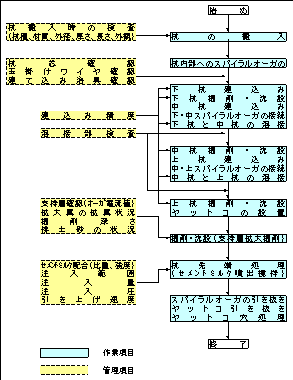
図-1鋼管杭の中掘り先端拡大根固め杭 図-2 中掘り先端拡大根固め工法の標準 の概念図 的な施工フローと管理項目
(2)検査項目の選定
鋼管杭の中掘り先端拡大根固め工法は、鋼管杭を地中深い強固な支持地盤まで中掘
沈設し、杭先端部(支持層地盤)にセメントミルクを噴出撹拌して拡大根固め球根を築
造する方式である。このようにして施工した鋼管杭の中掘り先端拡大根固め杭の概念図
を図-1に示す。また、中掘り先端拡大根固め杭を施工する際の標準的な施工フローと
管理項目を図-2に示す。
図-2より、施工時の品質管理項目は、大きく分けて次のように分類することができ
る。
・杭の搬入時検査
・杭芯確認
・建込み精度
・溶接部検査
・先端部の定着管理
・先端処理管理
何れの杭においても施工した杭の品質で最も重要視されているのは、支持力である。
中掘り先端拡大根固め工法では、杭の支持力を確認するには施工完了後、セメントミ
ルクを噴出撹拌して築造した拡大根固め球根が所定の強度を発現する28日程度以上
養生してからの載荷試験に依らねば成らず、打撃工法のように施工時に支持力を直接
確認することは事実上不可能である。したがって、中掘り先端拡大根固め工法では、
支持力に代表される杭の品質は、上記の各施工段階での品質管理の精度で判断されて
いるのが現状である。
上記の品質管理項目は何れも重要な項目であるが、その内、特に支持力の問題への
影響が大きいのは、「先端部の定着管理」、「先端処理管理」である。その中でも、杭
先端を支持層に確実に定着させるための支持層の確認、杭先端下方に築造する拡大根固
め球根の形状・寸法およびその強度管理に関するものであると考えられる。つまり、中
掘り先端拡大根固め工法では、杭先端を所定の強固な支持層に確実に根入れして、杭先
端下方に所定の拡大根固め球根の形状・寸法および強度を有するものを築造し得たかが
、 杭の支持力発現に最も重要な要素となる。
現状では、「支持層の確認」、「拡大根固め球根の形状・寸法」および「強度」の3つ
の管理手法について、次のような問題点があると考えられる。
1)支持層の確認手法
現状の管理手法は、オーガの電流を測定し、その負荷電流と土質柱状図、さらには掘削
土砂の性状等より総合的に判断して支持層を確認している。しかし、負荷電流には、
・地盤
・掘削速度
・杭径
・杭長
・施工機械(駆動装置)
等の違いによってバラツキがあるため、例えば電流値がどの程度であれば支持層であ
るといったような定量的な判断は出来ない。
2)拡大根固め球根の形状・寸法の管理手法
現状の管理手法は、拡大ヘッドに取り付けている拡大翼の拡翼状況で確認している。
具体的には、拡大根固め球根を築造する拡大ヘッドは、いずれの工法も拡大翼が水平
たは上下に開閉するものであり、その機構は土の抵抗で開閉する仕組みになっている。
そこで、現状での拡大翼の拡大状況の確認手法は、拡大翼を拡翼した後、一旦回転を
止めて引き上げ、拡大翼が杭先端に接触する際の抵抗で確認している。しかし、この機
構のものは、機構的にいって拡大翼は確実に拡翼するものと考えられるし、現に掘り出
し試験によって所定の形状・寸法の拡大根固め球根が出来ていることも確認しているが、
実施工において実際どの程度拡大しているのか、完全に拡大しているのか確認出来ない
のが実状である。
3)拡大根固め球根の強度管理手法
現状の管理手法は、モルタルプラントから採取した試料で、拡大根固め球根を築造する
際に注入するセメントミルクの比重および強度を管理している。この手法は、実際せ
こうした拡大根固め球根の強度管理をしているわけではない。
以上のようなことから、現状の中掘り先端拡大根固め工法では、設計で要求されてい
る性能の杭を施工において確実に構築し得ているとは言い難い。
そこで、本事業では、杭の支持力に最も影響を及ぼす上記3項目を含めた以下に示す
検査項目を選定した。
・支持層の確認
・拡大根固め球根の形状・寸法(球根径と球根高さ)
・拡大根固め球根の強度
・拡大根固め球根を築造する際に注入するセメントミルクの注入量
・杭先端の位置
・時間
(3)検査項目の具体的な計測項目・センサーやパソコンのデイスプレイへの
出力画面の検討
ここでは、(2)で選定した検査項目について、基本的には杭一本々を施工中に検査
する事を念頭において、具体的に何をどのようなセンサーで計測するか検討した。その
後、杭施工時の状況を管理検査するためにパソコンのデイスプレイへ何を出力するか等
について検討した。
1)検査項目の具体的な計測項目およびセンサーについて
各検査項目に対する具体的な計測項目およびセンサーについては、表-3に示して
いる。
表-3 検査項目の具体的な計測項目およびセンサー
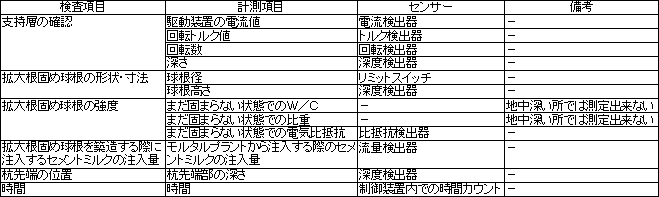
2)パソコンのデイスプレイへの出力画面の検討
杭施工時の状況を確認するために、各種センサーで計測した値をパソコンのデイスプ
レイに出力する必要がある。パソコンのデイスプレイへの出力画面としては、杭が支持
層へ到達するまでの中掘り沈設時の様子と、支持層到達後に杭先端下方に拡大根固め球
根を築造する際の様子を見るために、図-3に示すように中掘り沈設時と拡大根固め
球根築造時の様子を出力するようにした。
③
事業成果(概要)
(1)ターゲットとする施工法としては、近年市街地において鋼管杭で主流をなして
いる中掘り先端拡大根固め工法とした。
(2)検査項目としては、中掘り先端拡大根固め工法で施工した鋼管杭の支持力に最
も影響を及ぼすと考えられる「支持層の確認」、「拡大根固め球根の形状・寸法
」および「強度」の3項目を含めた以下の項目を選定した。
・支持層の確認
・拡大根固め球根の形状・寸法
・拡大根固め球根の強度
・拡大根固め球根を築造する際に注入するセメントミルクの注入量
・杭先端の位置
・時間
(3)検査項目について、基本的には杭一本々を施工中に検査する事を念頭において具
体的に何をどのようなセンサーで計測するかについては、表-3に示している。
その結果、拡大根固め球根の強度以外の項目については、計測項目とそれを計測す
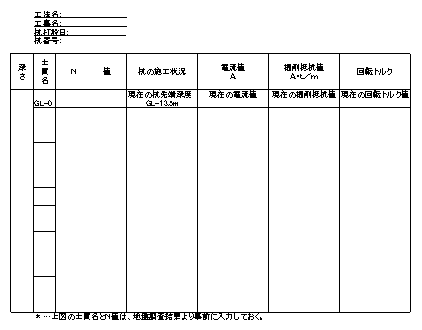 |
(a)中掘り新設時の出力画面の例
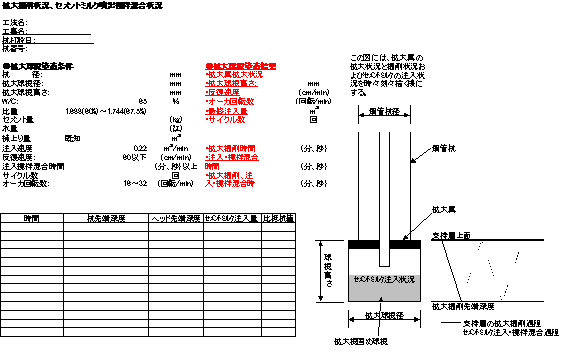 |
(b)拡大根固め球根築造時の出力画面の例
図-3 パソコンのデイスプレイへの出力画面の例
るためのセンサーを選定する事が出来た。拡大根固め球根の強度については、まだ
固まらない状態で固まった時の強度と関係の深い水セメント比(W/C)と比重計
測をリストアップしたが、この両者については、地上では測定可能であるが地中深
い所で測定する方法が見つからなかった。したがって、強度については今のところ
施工中に検査する手法はないが、それであれば、拡大根固め球根の練り上がり状況
だけでも間接的ではあるが検査出来ないかと言うことで、電気比抵抗の測定を試み
ることにしている。ちなみに、電気比抵抗というのは、電気の通しにくさを表す指
標である。
パソコンのデイスプレイへの出力画面については、杭が支持層へ到達するまでの
中掘り沈設時の様子と、支持層到達後に杭先端下方に拡大根固め球根を築造する際
の様子の2つに分けて、図-3に示すように中掘り沈設時と拡大根固め球根築造時
の様子を出力するようにした。